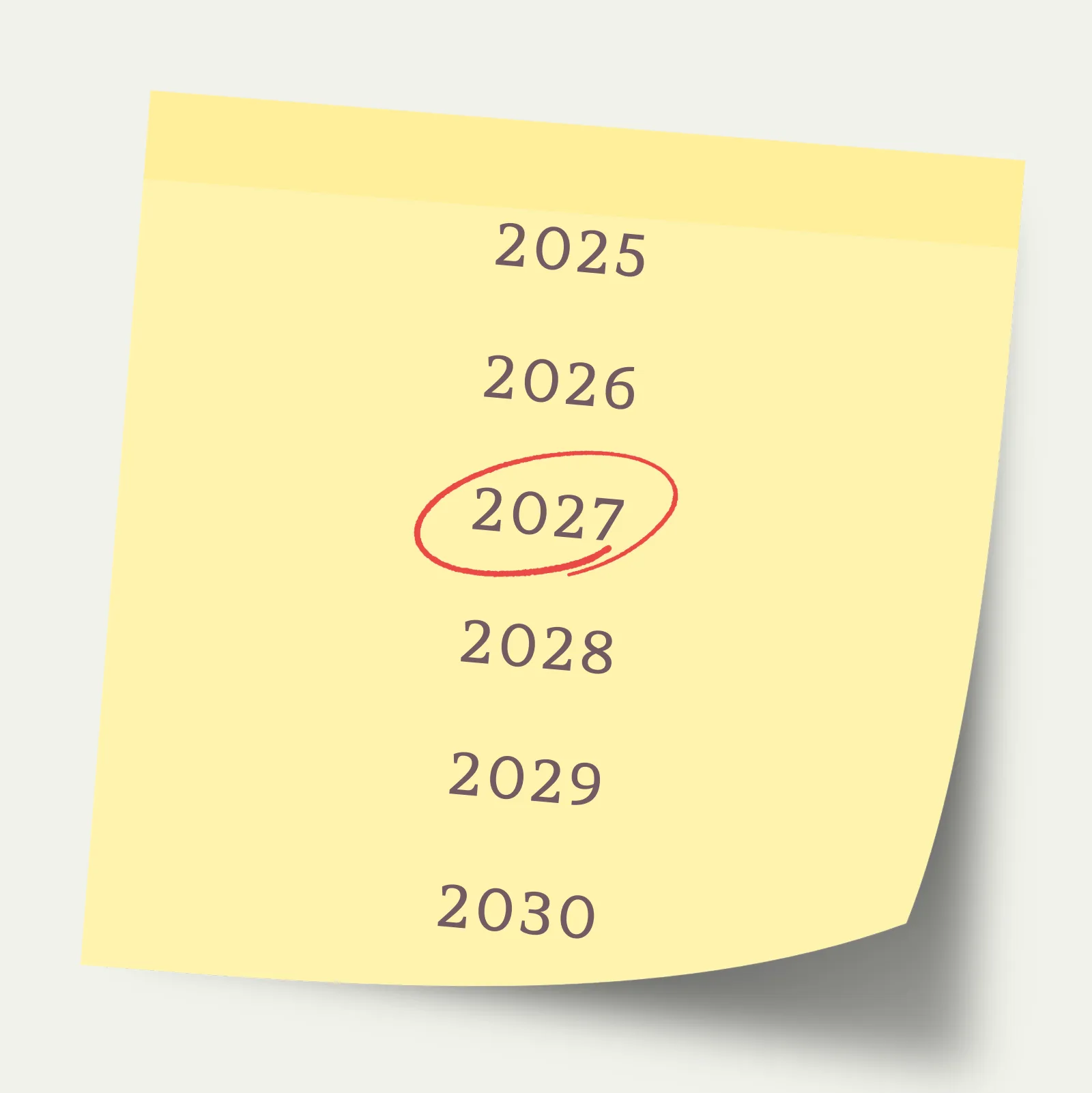COLUMNコラム
2025.09.16
2026.01.14
振袖を着るときに必要なものチェックリスト|着付け小物の一覧も紹介

成人式や結婚式など、特別な日に着る振袖は、華やかな着姿を完成させるために多くの準備が必要になります。振袖本体だけでなく、帯や小物、さらに着付けに必要な和装アイテムを揃えることで、美しい仕上がりを実現できます。しかし、普段は和装に触れる機会が少ないため、何を用意すべきか迷う方も少なくありません。
当記事では、振袖を着るときに必要なものを一覧で紹介し、準備のポイントを分かりやすくまとめます。成人式や結婚式に振袖を着るか検討中の方は、ぜひお役立てください。
振袖を着るときに必要なもの一覧
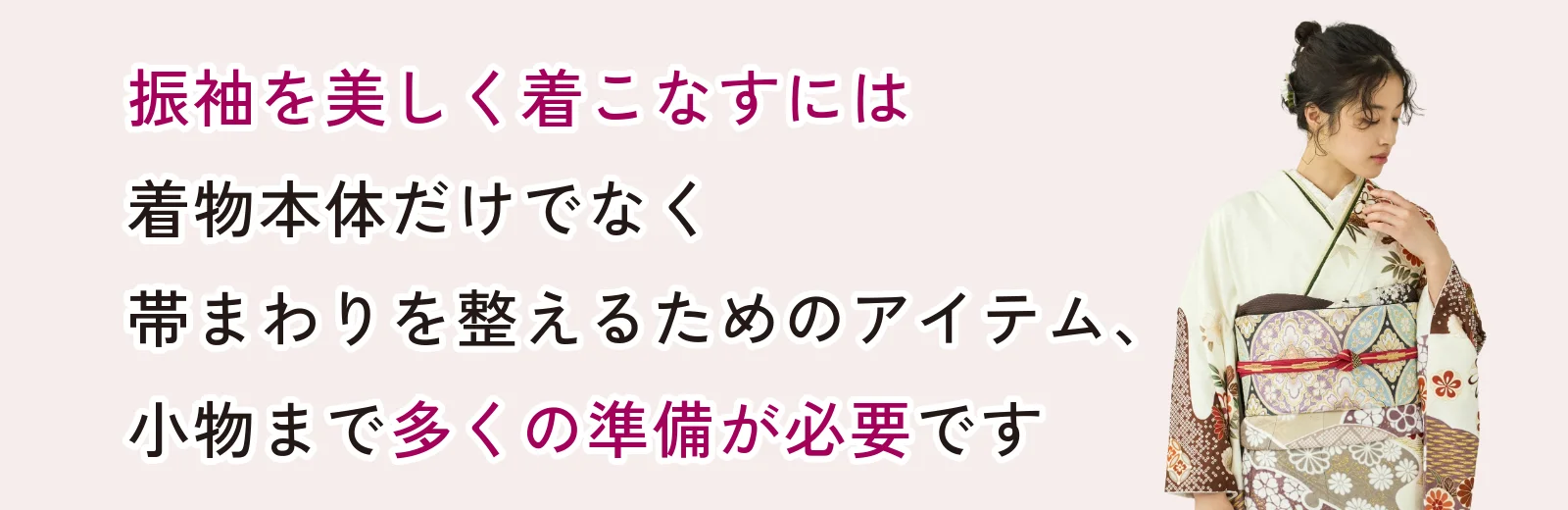
振袖を美しく着こなすには、着物本体だけでなく、衿元や帯まわりを整えるためのアイテム、さらに小物まで多くの準備が必要です。ここでは振袖を着るときに必要な基本アイテムと、それぞれの役割について解説します。
成人式・振袖レンタルの費用相場はどのくらい?
メリット・注意点も解説
振袖
振袖は、袖丈が長い華やかな着物で、未婚女性の第一礼装とされています。成人式や結婚式、格式ある式典でよく着用され、日本の伝統美を象徴する装いです。袖の長さによって「大振袖」「中振袖」「小振袖」と格が分かれ、成人式では中振袖が一般的です。
振袖を美しく着こなすには、袖丈が長襦袢の寸法と揃っていることが大切です。購入品やレンタル品、譲り受けたものを使う際には事前に袖丈を確認しておくと安心です。優雅さと華やかさを兼ね備えた振袖は、特別な日の装いを格調高く演出します。
長襦袢(ながじゅばん)
長襦袢は、肌襦袢の上・振袖の下に重ねて着る和装用の下着で、見た目には衿元や袖口から少しのぞく程度ですが、とても重要な役割を担っています。摩擦の少ない滑らかな生地で仕立てられており、着物の滑りを良くして着崩れを防ぎ、さらに汗や皮脂汚れから振袖を守ります。
振袖と合わせる際には、袖丈や肩裄が振袖ときちんと合っていることが必須です。寸法が合わないと袖口から長襦袢がはみ出してしまい、見た目に違和感が出るため注意が必要です。また、半衿を取り付けることで衿元を華やかに見せられ、コーディネートの楽しみも広がります。防寒の役割も兼ねるため、式典の日を快適に過ごすために大切なアイテムです。
半衿(はんえり)
半衿は、長襦袢の衿に縫い付けて使う布で、首まわりの汚れから長襦袢や着物を守る役割を持ちます。幅は約15cm、長さは1mほどあり、肌に直接触れる部分に当たるため、定期的に洗ったり付け替えたりして清潔に保つことが大切です。
白無地が基本で、刺繍や色柄入りを選ぶと顔まわりが華やかになり、振袖姿をより美しく見せられます。縫い付けるのが一般的ですが、安全ピンやテープで留めるなど手軽な方法もあり、実用性とおしゃれを兼ね備えたアイテムです。
重ね衿・伊達衿(かさねえり・だてえり)
重ね衿(伊達衿)は、着物を2枚以上重ねて着ているように見せるための装飾用の衿です。長さは約1.2m、幅は11cmほどで、半衿より細長い形状をしています。礼装シーンで振袖や訪問着などに合わせることが多く、衿元に差し込むことで華やかさを演出できます。
もともとは複数の着物を重ねて着る風習の名残から生まれたものです。白が基本の半衿と違い、重ね衿(伊達衿)には鮮やかな色柄が多く、コーディネート次第で胸元をより印象的に彩ることができます。
袋帯(ふくろおび)
袋帯は、丸帯を簡略化した帯で、表と裏に異なる織り方をした二重仕立てが特徴です。長さは約4m50cm、幅は約31cmあり、振袖や留袖など第一礼装に合わせられる格の高い帯とされています。
金銀を用いた華やかなものから控えめなデザインまで幅広く、結婚式や成人式などのフォーマルな場にふさわしい装いを演出できます。また、訪問着や付け下げ、色無地などセミフォーマルにも合わせやすく、用途の広さから人気を集めています。
帯揚げ(おびあげ)
帯揚げは、帯結びに使う帯枕やその紐を隠すために用いる布で、振袖や着物姿をより美しく整える役割があります。実際に見える部分はわずかですが、色や質感がコーディネートのアクセントとなり、全体の印象を引き締めます。振袖用にはふくれ織や絞りの帯揚げが多く用いられ、ふんわりとした質感でボリュームを出せるのが特徴です。
成人式では華やかに見えるように、その他の場面では控えめに見せるなど、結び方によって雰囲気を変えられる点も魅力です。
帯締め(おびじめ)
帯締めは、帯の上から巻いて固定するための小物で、振袖や訪問着、留袖といった礼装をはじめ、着物には欠かせないアイテムです。帯の中央に結ぶことで緩みを防ぎ、着姿を安定させる役割を果たします。振袖用は長さ約150cmが一般的ですが、変わり結びが可能な170~190cmの長尺タイプもあります。
かつては帯揚げや重ね衿と色を揃えるのが主流でしたが、現在は自由な配色で個性を出すスタイルも増えています。帯締めの色選びによって振袖全体の雰囲気やバランスが大きく変わるため、コーディネートの重要なポイントとなります。
草履・バッグ
振袖に合わせる草履は、フォーマル用を選ぶのが基本です。草履台が5cm以上あり、白・金・銀など光沢のある素材を使ったものが格式に合います。鼻緒も高級感のある唐織や刺繍入りを選ぶと華やかさが増します。
バッグは振袖の柄や帯との統一感を意識するのがポイントです。古典柄の振袖には古典柄バッグを合わせるなど全体を調和させると上品に仕上がります。また、草履とバッグをセットで選ぶとバランスがとりやすいです。
髪飾り
振袖姿にアクセサリーは基本的に用いないため、華やかさを添える小物として髪飾りが重要な役割を担います。振袖の柄や色に合わせて選べば全体に統一感が出て、より印象的な装いに仕上がります。
髪飾りには生花やドライフラワー、リボン、つまみ細工などさまざまな種類があり、清楚系・キュート系・古典系など、なりたいイメージに合わせて選べるのも魅力です。特に生花は発色や香りで特別感を演出でき、白は万能カラーとして清楚な印象を与えます。一方で赤は振袖と合わせやすい定番色です。選ぶ際は振袖や帯に使われている色を取り入れるとバランスがよく、髪飾りだけが浮く心配もありません。
振袖の着付け時に必要な小物一覧

振袖を美しく着こなすには、着物本体や帯だけでなく、多くの着付け小物が大切です。ここでは肌着から帯まわりまで、必要なアイテムを順番に紹介します。
肌襦袢・肌着・和装スリップ
肌襦袢は着物の下に着るインナーで、汗や皮脂から着物を守る重要な役割を持ちます。長襦袢とは別物であり、「肌襦袢→長襦袢→着物」の順に着用するのが基本です。綿素材など吸湿性の高い生地が多く、洗濯が容易で手入れも簡単です。色は白や薄ピンクなど目立たないものが主流で、袖や衿から外に見えないよう工夫されています。
裾よけと合わせると歩きやすさが増し、夏は汗を吸収し冬は保温効果を発揮します。ワンピース型の和装スリップも便利で、快適さと清潔感を保ちながら振袖を美しく着こなせます。
足袋
足袋(たび)は和装用の靴下で、草履を履く際に鼻緒を挟めるよう指先が分かれているのが特徴です。足首部分には「こはぜ」と呼ばれる留め具が付いており、しっかりと固定できます。履くときはこはぜを下から順にかけるのが一般的で、肌着やステテコを着た後に履くと着崩れを防げます。
足袋には白足袋・色足袋・柄足袋などの種類がありますが、振袖のように第一礼装にあたる着物を着る際には、白足袋を用意するのが正式とされています。フォーマルな場にふさわしい清楚で格式高い印象を与え、成人式や結婚式などにも安心して臨めます。
補正パッド・フェイスタオルなど
振袖を美しく着こなすためには、体型に合わせた「補正」が必要です。振袖は洋服のようにウエストを強調せず、凹凸をなくした「ずん胴」体型に整えることで、きれいなラインに見えます。そのため成人式や結婚式といった特別な日に着る際は、補正で体のラインを整えることが大切です。
補正に使う代表的なアイテムはタオル・ガーゼ・補正パッドです。タオルは腰や胸に当てて凹凸をなくすのに使い、3~5枚ほど用いるのが一般的です。ガーゼはタオルを固定するために巻き付けて使用します。着物専用の補正パッドを利用すれば、タオルを重ねる手間を省いて簡単に補正が可能です。
衿芯
衿芯は、長襦袢の衿部分に差し込んで使う和装小物で、着物の衿元を美しく整えるために必要なアイテムです。振袖は格式の高い礼装であるため、衿元がふにゃりと崩れてしまうと見映えが損なわれますが、衿芯を入れることで衿がピンと立ち、凛とした印象に仕上がります。
素材には、張りのあるポリエチレン製や柔らかい綿製、通気性のよいメッシュタイプなどさまざまな種類があります。厚手は衿をしっかり立て、薄手は首への負担が少ないのが特徴です。初めての方はスタンダードなポリエチレン製を選ぶと扱いやすいでしょう。
腰紐
腰紐(こしひも)は、着物を着付ける際に着崩れを防ぎ、丈を調整するために結ぶ細長い紐です。腰回りで使うだけでなく、胸元を押さえる「胸紐」や一時的な仮止め用としても活躍します。素材には締めやすく緩みにくいモスリンや正絹のほか、綿や麻、ポリエステルなどがあり、用途や季節に合わせて選べます。
初心者には扱いやすく手頃なモスリン製がおすすめです。振袖の着付けでは複数本必要になるため、事前に準備しておくと安心です。
コーリンベルト(きものベルト・着付けベルト)
コーリンベルトは、着物の衿元を美しく整え、着崩れを防ぐために使う便利アイテムです。昭和に誕生したゴム製ベルトで、両端に付いたクリップを衿に挟んで使います。長さ調節ができるため誰でも簡単に扱え、腰紐の代わりに用いることで衿元をすっきりと保てます。
必需品ではありませんが、あると着付けが楽になり仕上がりも安定するため、多くの方に利用されています。プラスチック製クリップのものは軽くて痛くなりにくく、長時間の着用にも安心です。
伊達締め
伊達締め(だてじめ)は、長襦袢や着物の衿元を安定させ、着崩れを防ぐために用いる幅広の紐です。一般的には長襦袢と着物に1本ずつ、計2本を使用します。幅は7~10cmほどあり、衿元を整えるほか、おはしょりをきれいに保つ役割もあります。
素材や形状は、博多織タイプや芯入りの化繊製、さらにマジックテープ付きや通気性の良いメッシュタイプなどさまざまです。着付けを快適にするために欠かせない小物の1つです。
前板(まえいた)
前板(まえいた)は、帯板(おびいた)とも呼ばれ、帯の前部分に挟んでシワを防ぎ、帯姿をすっきりと見せるための小物です。見えない部分ですが、仕上がりの美しさを大きく左右するため、振袖着付けには欠かせません。
一般的には厚紙に布を貼ったタイプやプラスチック製があり、ゴム付きで装着が簡単なもの、帯の途中に差し込むものなど種類も豊富です。成人式などのフォーマルなシーンには幅広タイプ、夏場には麻やメッシュ素材など涼しい仕様を選ぶと快適に着られます。
後板(うしろいた)
後板(うしろいた)は、振袖や花嫁衣裳などで袋帯を華やかな変わり結びにする際に、帯の後ろに入れて使う帯板です。前板が正面のシワを整えるのに対し、後板は背中側の帯を支え、シワを防いで結び目を美しく見せる役割を担います。通常のお太鼓結びでは不要ですが、飾り結びをする振袖や祝い帯には必要なアイテムです。
素材は白やピンクの樹脂製が一般的で種類は多くありません。専用の後板がなくても厚紙やPPシートで代用できるため必ず購入する必要はありませんが、美しい帯姿を保つためには用意しておくと安心です。
帯枕
帯枕とは、帯結びを立体的に美しく見せるための補助アイテムです。名古屋帯でのお太鼓結びや袋帯での二重太鼓、振袖ならではの華やかな飾り結びをする際、帯山に高さと奥行きを与える役割を果たします。帯枕を使うことで帯結びが安定し、長時間着用しても形が崩れにくくなります。
形や大きさ、膨らみ具合などさまざまな種類があり、結び方や体型に合わせて選べます。振袖をより華やかに着こなすためには欠かせない小物の1つです。
三重紐・四重紐
三重紐(さんじゅうひも)は、振袖の帯結びに必要な小物で、ゴムが三本並んだ仮紐のことです。両端に布の紐が付いており、帯をたたんでゴム部分に挟み込むことで羽根を作り、華やかな変わり結びを形づくります。振袖や七五三の帯結びでよく使われ、仕上がりを豪華に見せるのが特徴です。なお、お太鼓結びなど羽根を作らない結び方では不要です。
四重紐は、さらに複雑な帯結びを楽しみたい場合に使われるもので、羽根の数を増やす際などに便利です。振袖姿をより華やかに演出したいときに活躍する、特別感のある小物と言えるでしょう。
ショール
成人式の振袖姿に定番となっているのがショールです。習慣の始まりは昭和30年代で、当時の上皇后陛下が身につけたミンクのショールが話題になり、広く普及しました。
ショールは必須ではありませんが、防寒対策や華やかさの演出から、近年では用いられることが多い傾向にあります。成人式は真冬に行われるため、衿元から肩を温める防寒具として役立ちます。また、フェイクファーや羽毛など多彩なデザインがあり、振袖コーディネートをより豪華に見せてくれるおしゃれアイテムとしても人気です。
晴れの日の支度は万全に|振袖の必要なものは「きものやまと」にお任せを

成人式や結婚式など、一生に一度の大切な晴れの日には、振袖選びを万全に整えておきたいものです。「きものやまと」では振袖から帯、小物まで一式をワンパックで揃えることができ、安心して準備を進められます。
お手軽に利用できる「レンタルプラン」は、仕立上がり品から新品のオーダー仕立てまで幅広く選べるようになっており、自宅に配送され、クリーニング不要で返却できる仕組みになっています。さらに、ヘアメイクや着付け、記念撮影まで含まれる安心サポートパックを追加できるので、振袖を自由に楽しみたい方におすすめです。
一方で、購入プランを選べば、お気に入りの一着を自分のものにでき、何度でも着用することが可能です。25点フルセットとして小物まで揃えられるほか、お手入れや保管サービスも利用できるため、振袖を大切に扱いながら長く楽しめます。振袖から帯や小物までトータルで揃えられることにより、初めての方でも安心して支度を整えられます。
まとめ
振袖を着るためには、振袖本体や帯・小物に加えて、肌襦袢や腰紐、前板など着付けを支える和装小物が必要です。どれも美しい着姿をつくり、着崩れを防ぐために必要なアイテムとなります。
成人式や結婚式といった特別な一日を安心して迎えるためには、事前に必要なものをしっかり確認し、準備を整えておくことが大切です。振袖選びや小物の一式はぜひ「きものやまと」で揃えていただき、安心して晴れの日をお楽しみください。
この記事を書いた人
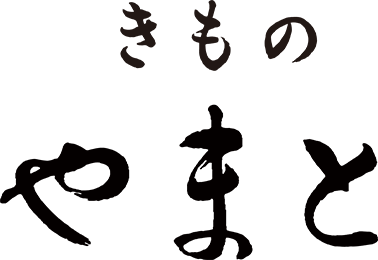
デザイナー 徳井愛子
現デザイナー職に就く前は、きものやまと店舗スタッフとして、多くのお客様のハレの日のお手伝いをして参りました。ふりそで選びは勿論、サポートに至るまで、これまでの豊富な経験をベースに、お客様に寄り添い、お役に立つ情報をお届けいたします。
監修者
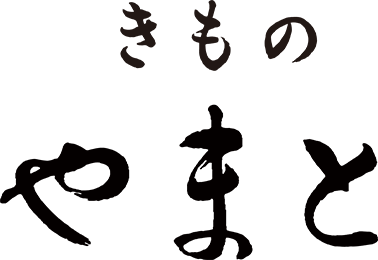
きものやまとデザイン部
創業109年のきもの専門店「きものやまと」。さんちと共に、文化と伝統を受け継ぎ、新しい暮らしに寄り添う、きものやまとのオリジナル着物を創作・ご提案しています。お客様の日々とハレの日を彩る振袖がいい出会いとなるよう、心を込めてお手伝いいたします。